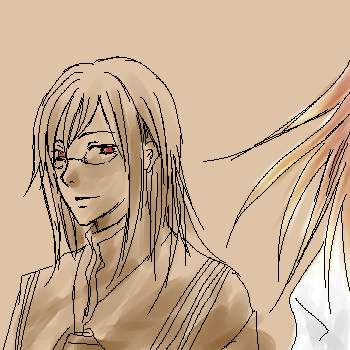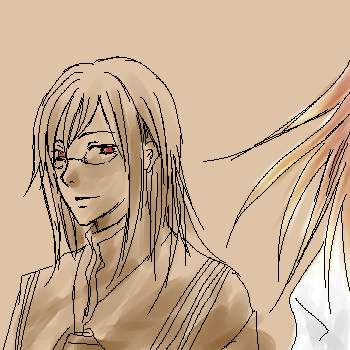戦場には血が流れる───
そんな至極当然のことを、改めて少年は知ることになった。
むせ返るような悪臭に、自分の中にも流れる同じ体液が飛散したその土地はもはやクリフォト以上の狂気に満ちている。
そんな戦場で意志を保ち続けるのは非常に難儀なことだと、若い皇帝が言っていたのを思い出す。
しかし自分はまだ狂うことなく自我を保ち続けていられる。
それもやはり劣化だからなのかと自虐的に自分を蔑むその意志そのものが、ルークの病であり自我の崩壊とも言えるだろう事を、
まだこの時の少年に気付けるはずもなく。
ルークは剣にこびり付いた血と油を振り落とすと仲間の元へと歩を向けた。
しかしその歩みは二歩以上、その先へ進むことはなかった。
「………なに」
自分の利き手を取るグローブに包まれた手を困惑の面持ちで眺め、ルークは抗議する。
しかし、その手の持ち主は答えずそのまま掴んだ腕を引っ張り見方陣営とは逆の、鬱蒼と木が生え茂る森へとルークを連れ込んだ。
捕まれた掌越しに、男の体温の高さを知る。
反射的にコクリ、と鳴る喉をルークは隠せずしかしそれを気にする暇もなく衣服を剥ぎ取られ、なんとも屈辱的な態勢を取らされた。
これは何というのだろう…とルークは何度目かになる男からの行為を快楽のさざ波に揺れる思考で考える。
これが、あの若い皇帝の言っていた狂気に精神を蝕われた者のせめてもの抵抗なのだろうか。
それにしては……
「──ッ、ほらっ飲みなさい──!」
「んぐっ、んぅーーーーっっっ!!」
見開かれた翠玉の瞳からは、更に宝石を思わせるほどの玉が次々と零れ落ちていく。
それを下で舐め取った男はその塩辛さに少し眉を寄せ、気に入らなかったのだろうかそのまま地面へと吐き出した。
「泣くんじゃありませんよ、まだ」
「う……もっ声……」
何度も何度も絶頂を与えられ、遠慮無しに泣かされ続けたのだ。
ルークの声は可哀相なほど涸れ、水分を求めている。
男はいつものあの声が好きだった。
あの声で泣かせるのが好きだった。
だから考え、手元に落ちていた朽ちた兵士の剣を取り迷い無くその腕に当てた。
瞬き、そして男の腕からこの土地に染み渡ったあの色が流れ落ちた。
ルークはヒッ─と息を飲み必死にかぶりを振る。
しかしその頭の後ろにもう片方の手を差し込み、唇をすれすれ間で近づけさせ
「さあ飲みなさい」
命じた。
「あ─ッ、あぁっ──!」
引き攣った顔で幼子が唯一自由な目線だけを自分に向けてくる。
しかし男は許さなかった。
「ルーク」
子供をあやすような声と表情でそう呼べば、ちろり、と覗く舌先に男は満足げな笑みを浮かべる。
その恐怖と嫌悪を刻む唇に背徳的な赤が濡れた時、
ジェイドが悪魔さえもおののく笑みをこぼしたことなど。
穢す楽しみを知る者だけが得る、世界の快楽。
|
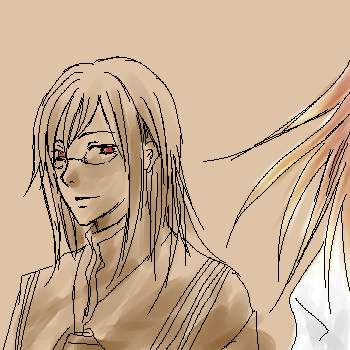
|