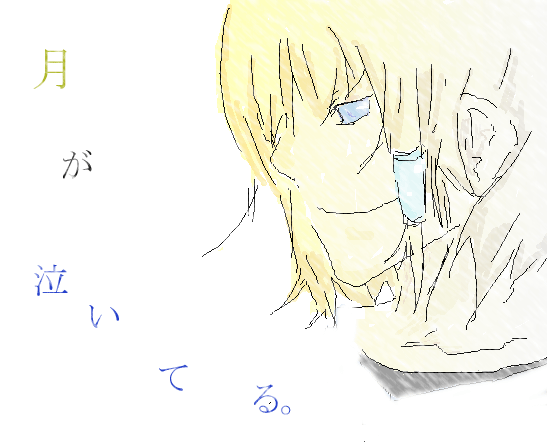
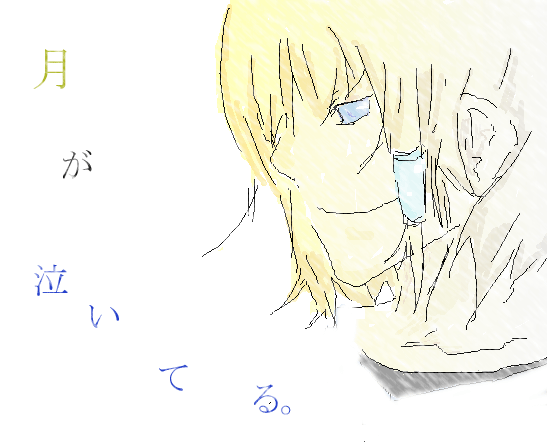
| その日はいやに月が綺麗だったので、俺は重たいまぶたを押し上げて透明な壁のさえぎる空を見上げた。広すぎる闇を覆うようにきらめいている星よりはささやかな光にどこか懐かしさを覚え、思考に一瞬走った面影に切なさを感じた。夜は、ただ夜というだけで気分が落ち込むこともある。 この静けさがどうしようもなく寂しいなどと、誰にも言ったことはない。 自室の広すぎる自分のベッドに寄りかかるようにして、月に視線を注ぐ。 やわらかい、あの色が好きだ。 すきだ、とても。 真新しいシーツに散らばる自分の髪の色も似たような色をしているが、あんな儚さの滲んだ美しい色はしていない。むしろ……と、思い出しかけてそれにしばし思考を奪われる。無駄なことを、叶わないことばかりを思う。 朝が来なければいいのに、そうしたらずっと見ていられる。 この美しく、やさしい月を。 自分の弱さを叱咤することもなく、感傷に浸っていたい。 日が昇れば忘れたフリをしなければならないこの思いは、つらいばかりだ。 思う相手に会いたいと、ただそれだけの願いすら口にできない。 夜にまぎれた雨雲が、しとやかに音を立てて近づいてくる。 月を隠すように雨が降るので、オレは月が泣いているのではないかと思った。 月が泣いてる。 ああ、泣いているのはオレの方か。 「はやくかえってこい」 本人を前にしてはいえなかった言葉を月に向かって吐き出した。 誰にも見せないオレの弱みを、ただ月だけが知っている。 9・9 ウパラの日単発 |