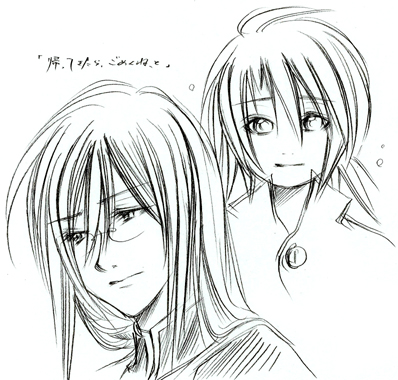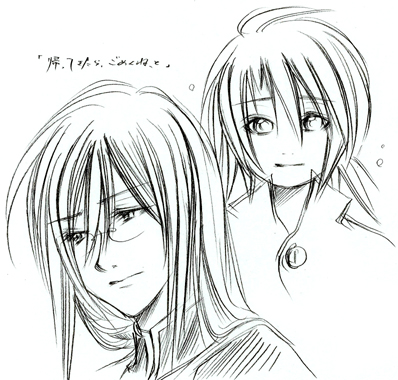
帰ってきたら、ごめんね、と 柔らかい肌も、見つめてくる碧の瞳も、鮮やかな髪の色までも、どこも同じなのだ。 どこも、変わらないのだ。 「 」 「……ルーク?」 目の前に、あれだけ焦がれた姿が現れ、 目の前で、あれだけ焦がれた姿が動く。 それでも、 それなのに、――ただ、そこに在るだけだ。 「 」 「ルーク、……ルーク、聞こえません、なんと、……言ってるのですか」 柔らかな頬を両手で包んで、よくやっていたように視線を合わせる。 穏やかな笑みは以前のような諦め気味のそれではなく、心から安らかで、けれどとてもはかない。 「ルーク、私は……、あなたにずっと、言いたかったことが……」 喉の奥はこんなにも痛くなるものだと、初めて知った。 声はこんなにも出なくなってしまうのだと、初めて感じた。 どうしてこんなときに限ってこうなのだ。己を罵ってみても始まらない。 すきとおった碧の瞳は、あいもかわらず心のおくのおくそこまでもを、どこまでもどこまでも見通してくる。 言いたいことが、確かにあった。 言わなければならないことがあったのだ。 それすらも、言葉として出てはこない。 今、口を開けば、確実に――、 「 」 泣いて、しまう … … 「ルーク、……すみません……」 ぐ、と手のひらを握り締め、声を絞り出す。 あふれそうになる涙をこらえるために、手のひらにつめを立てた。 ルークがさっきから繰り返し繰り返しつぶやく言葉が、同じ単語だと気づいたのだ。 気づいてしまって、また、喉が締め付けられた。 あんなにもひどいことを言った。 あんなにもひどいことを言ったのだ。 それなのにこのこどもは、まだこうして名を呼んでくれている。 「すみません、……私は、ずっとあなたに、謝りたかった……」 謝って済む話でもない。謝れば愛すべきこのこどもが帰ってくるわけでもない。 おそらくは、己が楽になりたかったから、だ。 ずっと謝りたいと思っていた、理由は。 謝ったところで、彼が帰ってくるはずもない。 己が許されるはずもない。 それでも、言っておきたかった。 こんな夜更けに、音もなく現れてくれた最愛のこどもに、どうしても伝えておきたかったのだ。 「ルーク、私は今でも、あなたを……待っています」 けれど、やはり口にすることは出来なかった。 ただ微笑むだけのこどもに、謝罪の言葉はかけられてもそれ以外の言葉は告げられなかった。 「 」 「……ルーク、すみません、私には……、あなたの声がきこえない……」 赤い髪のこどもは、夜の冷えた空気にとけるように、ふんわりと笑った。 やってきたときと同じように、こどもは音もなく帰ってしまった。 また、ひとり のこされた。 「今でも、私は…………、」 好きです、と。 いつになったら、相手の目を見て言えるのだろう。 いつになったら、相手の目を見て謝れるのだろう。 あなたに死んでほしかったわけではないのだ、と。 言い訳がましく聞こえてもいい。 ごめんなさいと、ありがとうと、愛してます、と。 伝えられる日が、くればいい。 |